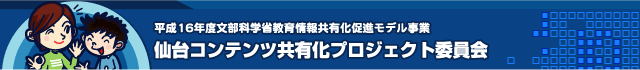
| 水よう液の性質とはたらき |
単元の目標
水溶液にはなにがとけているかに問題をもち,水溶液には気体や固体がとけているものがあることを調べる。また,リトマス紙を使うと水溶液を酸性,中性,アルカリ性になかま分けできることをとらえることができるようにする。次に,身のまわりの水溶液と金属の資料などから,水溶液は金属を変化させるかに問題をもち,多面的に追究していくなかで,金属が水溶液によって質的に変化していることをとらえることができるようにする。
本時の目標
・薬品をあつかうときに気をつけることを理解する。
・塩酸,炭酸水,食塩水,石灰水,アンモニア水にはどんなものがとけているか,蒸発させて調べることができる。
活用コンテンツ
学校放送ONLINE
小学校6年理科「3つのとびら」→第11回「水溶液を見極めよ」→「先生の部屋」→クリップ
http://www.nhk.or.jp/rika6/ja/frame.html
|
直接においをかいじゃだめなんだな
|
 |
正しいにおいをかぐ方法を調べてみよう。
|
本時の流れ
| 段階 | 学習活動
■使用コンテンツ・URL,▲指導上の留意点,●評価の視点 |
| 導入 | 1.5つの透明な液体の中から5年生の時に学習した食塩水を探すにはどうしたらよいか考えさせる。 |
| 展開 | 2.薬品を扱うときの注意点を理解しよう。 ▲コンテンツを視聴させたあとどんなことを注意すればよいか発表させる。 ▲実験結果と食塩水が入っていた試験管を予想させワークシートに記入させる。 |
| まとめ | 4 食塩水が入っていると思う試験管がどれだったか,またその理由を発表させる。 ▲5年生の時の学習を思い出させて,においがなくて白いものが残ったものが食塩水が入っていた試験管であったことを導き出させる。 |
授業の様子
コンテンツによってピペットの使い方やにおいをかぐ方法を理解し,実践することができた。
授業者の感想
・教科書の図で説明するときにくらべ児童は実験の手順や注意点がわかったようだった。
・動画コンテンツを途中で止めたり,繰り返すことでポイントつかませることができた。
| Acrobat Readerのダウンロードはこちら |